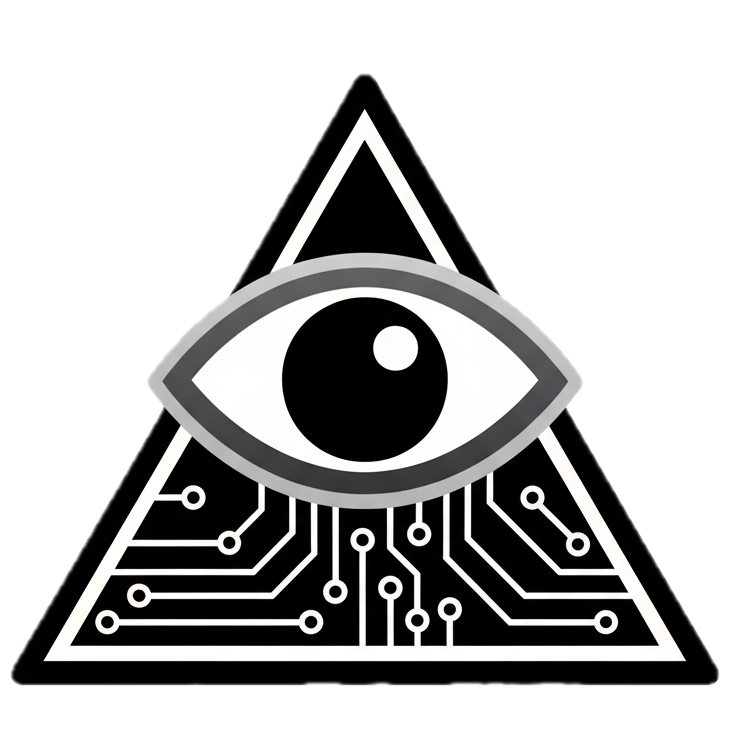導入:デジタル時代の心の脆弱性
Jenny Jiao HsiaとAP Thomsonが手掛ける新作ゲーム「Consume Me」は、単なるパズルゲームではありません。これは、開発者Hsiaの10代の摂食障害とダイエット文化にまつわる生々しくもユーモラスな回顧録であり、現代社会における心のセキュリティと自己防衛のあり方を深く問いかける作品です。
ゲームは、カロリー計算や体重管理といった「数字」に支配されるダイエット文化を、テトリスのようなパズル形式で表現。プレイヤーは、主人公ジェニーの視点から、食べ物を「バイト」(カロリーの代わり)として捉え、自己課された制限の中で食事を「管理」する日々を体験します。これは、外部からのプレッシャーや内なる葛藤が、いかに個人の精神的な「システム」を脆弱にし、絶え間ない「監視」と「制御」を強いるかを示す、強力なメタファーとなっています。
「バイト」という名の脅威:ゲームメカニクスが示す心の攻防
「Consume Me」の核心は、食べ物をテトリスブロックとして扱い、「バイト」という数値で管理するゲームメカニクスにあります。これは、摂食障害が「歪んだ戦略ゲーム」として機能する様子を巧みに表現しており、プレイヤーはジェニーの頭の中で常に走り続ける「計算」を追体験させられます。
- 食べ物の数値化:トマトやケール、パスタが「バイト」として数値化され、食事は「パワーの源」ではなく、「制御すべきもの」「恐れるべきもの」へと変貌します。これは、情報過多な現代において、健康や美に関する情報が個人の精神に与える「攻撃」の性質を象徴しています。
- 「バイト」制限と選択のジレンマ:ランチで「バイト」を摂りすぎると、自由時間に運動を強いられ、学業や人間関係を犠牲にするかどうかの選択を迫られます。これは、外部からの「脅威」(社会的な期待、自己イメージ)に対処するために、個人がどのように「リソース」を配分し、「自己防衛」を図ろうとするかを示しています。
- 「テトリス」としての期待:「完璧な人生」を築くための目標は、次々と降ってくるテトリスブロックのようです。「綺麗で賢い」という一列をクリアしても、すぐに次の「期待」という名のブロックが押し寄せ、心の「システム」は常に過負荷状態に置かれます。
社会的圧力と「完璧な人生」という名の攻撃
ゲームは、ジェニーの母親からの体重に関する批判をきっかけに、ダイエットが始まる様子を描きます。これは、社会的な期待や他者からの評価が、いかに個人の精神的な防御壁を崩し、脆弱な状態へと追い込むかを示唆しています。
ジェニーの人生における様々な目標(デート、友情、大学進学)は、常にダイエットという「アンカー」に縛られています。読書や運動といったミニゲームは、ワリオウェアのような混沌とした操作性で、ジェニーの人生に漂う不安感を表現。これは、現代人が直面する多岐にわたるプレッシャーが、いかに個人の「システム」に「サービス拒否攻撃」を仕掛け、心の平穏を奪うかという、隠れた脅威を浮き彫りにします。
10年後の「解放」:セキュリティパッチとしての時間
ゲームの終盤、物語は10年後に飛躍し、摂食障害の明確な「解決」は描かれません。しかし、そこには大きな変化があります。食べ物はもはや「バイト」の計算対象ではなく、「ただのソーセージ」として認識されます。これは、長期間にわたる精神的な脆弱性と「攻撃」の期間を経て、個人が自己の「システム」を「復旧」し、健全な状態へと回帰するメタファーとして解釈できます。
この「解放」は、時間という名の「セキュリティパッチ」が、内なる葛藤や外部からのプレッシャーによって傷ついた心を癒し、自己との健全な関係を取り戻す過程を示唆しています。ゲームは、摂食障害が単に食べ物やイメージの問題ではなく、人生の「制御」という幻想と深く結びついていることを示し、その幻想からの脱却が真の心のセキュリティをもたらすことを示唆しています。
まとめ:ゲームが示す現代社会の隠れた脅威
「Consume Me」は、その生々しくも正直な描写を通じて、摂食障害という個人的な体験を、現代社会における心のセキュリティという普遍的なテーマへと昇華させています。このゲームは、サイバーセキュリティのような直接的な脅威を扱うものではありませんが、社会的な期待、自己イメージ、そして「制御」への執着が、いかに個人の精神的な「システム」を脆弱にし、内なる「攻撃」へと繋がりうるかを鮮やかに描き出しています。
「Consume Me」は、私たち自身の心の「防御機構」を見つめ直し、現代社会に潜む見えにくい「脅威」に対して、いかに「自己防衛」を図るべきかを問いかける、示唆に富んだ作品と言えるでしょう。
元記事: https://www.theverge.com/games/791220/consume-me-review-steam