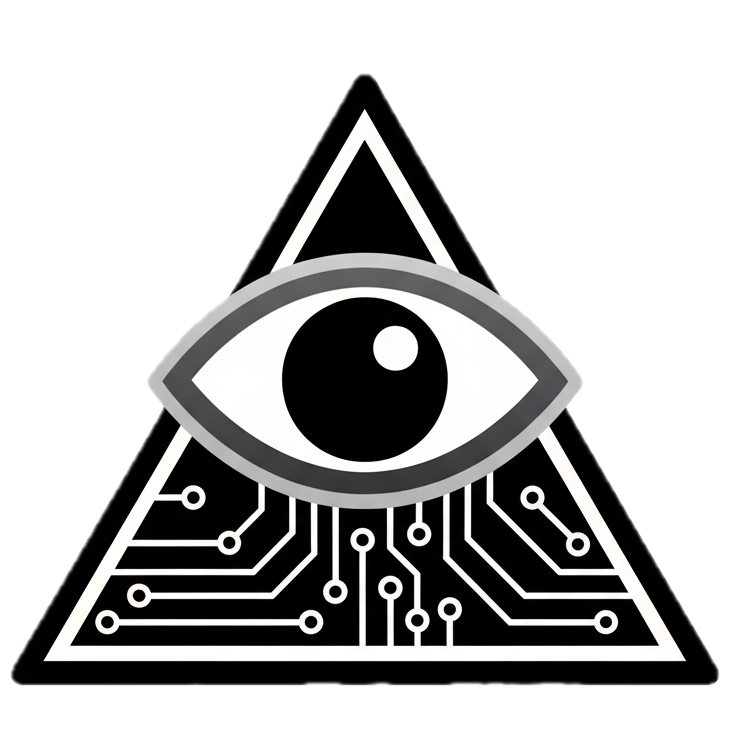OpenAIのGPT-5、数学的成果で物議を醸す
OpenAIの最新モデルGPT-5が数学分野で画期的な成果を上げたという主張が、AIコミュニティ内で大きな論争を巻き起こしています。OpenAIの研究者たちは、GPT-5が「これまで未解決だった10のErdős問題を解決し、さらに11の問題に進展をもたらした」と発表し、その功績を称賛しました。
しかし、この発表に対し、MetaのチーフAIサイエンティストであるヤン・ルカン氏は「彼ら自身のGPTardsによって吊るし上げられた」と痛烈に批判。Google DeepMindのCEOであるデミス・ハサビス氏も「これは恥ずかしい」とコメントし、OpenAIの主張に疑問を呈しました。
数学者からの反論と「誤解」
論争の火種となったのは、OpenAIのVPであるケビン・ワイル氏が投稿し、後に削除されたツイートです。ワイル氏はGPT-5がErdős問題を解決したと宣言しましたが、Erdős問題のウェブサイトを管理する数学者トーマス・ブルーム氏は、これを「劇的な誤解」であると指摘しました。
ブルーム氏によると、彼のウェブサイトで問題が「未解決」とされていたのは、単に彼自身がその解決論文を認識していなかったためであり、実際に問題が未解決であったわけではないとのことです。つまり、GPT-5は「これまで未解決だった問題を解決した」のではなく、「既存の文献に記載されている解決策を発見した」というのが実情でした。
文献検索の価値とOpenAI研究者の見解
この事実を認めつつも、OpenAIの研究者セバスチャン・ブベック氏は、「文献中の解決策が見つかっただけ」であることを認めながらも、これを「真の成果」であると擁護しました。彼は「文献を検索することがいかに難しいかを知っている」と述べ、GPT-5が膨大な学術文献の中から関連する解決策を見つけ出したこと自体に価値があるとの見解を示しました。
この一件は、AIの能力を評価する際の正確な表現と透明性の重要性を浮き彫りにしています。特に、科学的発見や未解決問題への貢献といった主張においては、その根拠と実態を慎重に検証する必要があることを示唆しています。
元記事: https://techcrunch.com/2025/10/19/openais-embarrassing-math/