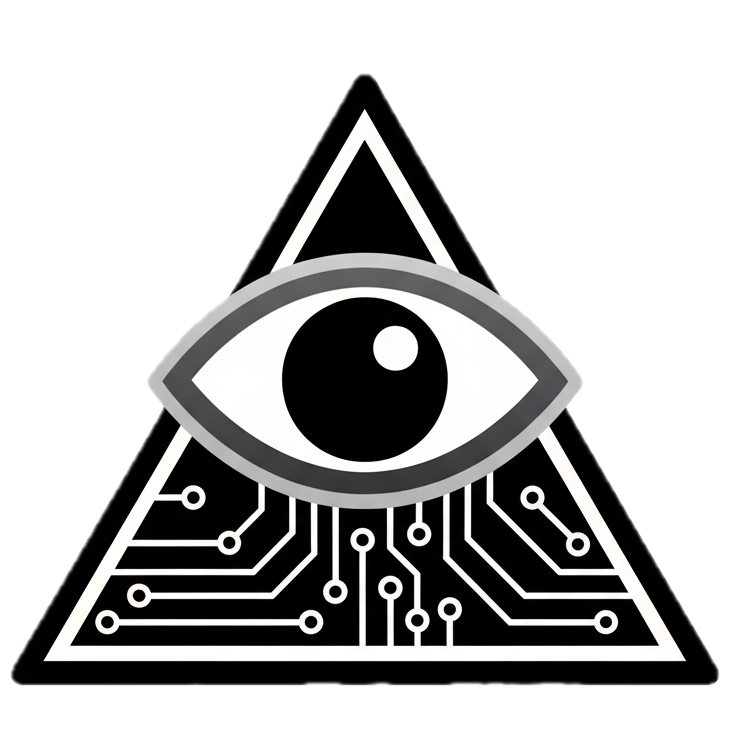OpenAIの数学的「偉業」と批判の嵐
OpenAIの最新モデルGPT-5が、数学界に衝撃を与える「偉業」を達成したと報じられましたが、その内容は後に「劇的な誤解」であったことが判明し、AIコミュニティ内で大きな議論を巻き起こしています。
当初、OpenAIのVPであるケビン・ワイル氏は、削除されたツイートで「GPT-5が10の未解決のエルデシュ問題を解決し、さらに11の問題に進展をもたらした」と宣言しました。この発表に対し、MetaのチーフAIサイエンティストであるヤン・ルカン氏は「彼ら自身のGPTardsによって吊し上げられた」と皮肉り、Google DeepMindのCEOであるデミス・ハサビス氏も「これは恥ずかしい」とコメントするなど、業界の重鎮たちから厳しい批判が寄せられました。
誤解を招いた「未解決問題」の真相
この「偉業」の真実を明らかにしたのは、エルデシュ問題のウェブサイトを管理する数学者トーマス・ブルーム氏でした。ブルーム氏によると、ワイル氏の投稿は「劇的な誤解」であり、GPT-5が「未解決の問題を解決した」というのは正確ではないと指摘しました。
ブルーム氏は、「GPT-5は、私が個人的に知らなかった、これらの問題を解決した文献を見つけただけだ」と説明しています。つまり、GPT-5は既存の解決策を発見したのであり、新たな数学的ブレークスルーを生み出したわけではありませんでした。
その後、OpenAIの研究者であるセバスチャン・ブベック氏も、「文献中の解決策が見つかっただけ」であることを認めつつも、「文献を検索することがいかに難しいかを知っている」と述べ、その情報検索能力自体は依然として価値のある成果であると示唆しました。
セキュリティニュースとしての考察:AIの主張と検証の重要性
今回のOpenAIの事例は、AI技術の進歩に関する主張の正確性と、その検証の重要性を浮き彫りにしています。特に、AIが社会の様々な側面、特にセキュリティ分野に深く統合されつつある現状において、その能力に関する誤解や誇張は深刻なリスクを招く可能性があります。
- 誤った信頼の構築:AIの能力が過大評価されると、AI駆動のセキュリティシステムや意思決定プロセスに対して、根拠のない信頼が構築される恐れがあります。
- 脆弱性の見落とし:AIが「解決した」と誤って認識された問題は、実際の脆弱性として残り、悪用される可能性があります。
- 透明性と説明責任の欠如:AIの成果に関する不正確な情報開示は、開発者や提供者に対する信頼を損ない、AI技術全体の健全な発展を阻害します。
AIの進化は目覚ましいものがありますが、その成果を評価する際には、厳格な検証と透明性が不可欠です。セキュリティの観点からも、AIの能力に関する正確な理解と、その限界を認識することが、安全なAIシステムの構築と運用には不可欠であると言えるでしょう。
元記事: https://techcrunch.com/2025/10/19/openais-embarrassing-math/